コンクリートの配合に、細骨材率という数値があります。細骨材率は、コンクリートのワーカビリティーを左右する重要な値です。
細骨材率を理解すると、配合表の単位量を見ただけで、おおよそのコンクリートの性状が想像出来るようになります。
この記事では、コンクリートの細骨材率(s/a)について、意味や計算方法、役割や基準などについて説明します。
コンクリートの配合計算について知ろう
細骨材率を説明する前に、まずは簡単に配合設計の流れを見てみましょう。
配合設計は以下の手順で進めていきます。
- 1粗骨材の最大寸法
- 2セメントの種類・スランプ・空気量
- 3配合強度
- 4水セメント比
- 5単位水量+単位セメント量
- 6単位粗骨材量・単位細骨材量
- 7混和剤量
今回の記事は6単位粗骨材量・単位細骨材量の部分についての説明です。
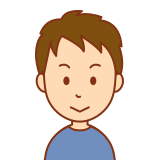
ちなみに、単位水量・単位セメント量・単位○○量の単位とは、コンクリートを1㎥製造する時の使用量のことを言います。
コンクリートの細骨材率(s/a)とは?
コンクリート1㎥当りの、細骨材(sand)と全ての骨材(all gravel)の比率を細骨材率と言い、sand / all gravelを略してs/aと表記します。
具体的には、細骨材の容積を全骨材(細骨材+粗骨材)の容積で割った値です。
割合は、質量比ではなく、容積比である事に注意してください。
細骨材率の計算式と計算例
下式が細骨材率を求める計算式です。
s/a=Sv/Av×100(%)
Sv:細骨材容積
Av:全骨材容積(細骨材容積+粗骨材容積)
例題1 計算例
細骨材量:910kg、細骨材密度:2.60g/㎤
粗骨材量:1080kg 、細骨材密度:2.70g/㎤
Sv=910/2.60
=350
Av=910/2.60+1080/2.70
=350+400
=750
s/a=350/750×100
=46.67≒46.7(%)
単位粗骨材量・単位細骨材量を算出する方法が2通りあります。
- 最適細骨材率による方法(土木学会)
- 最適単位粗骨材かさ容積法(建築学会)
どちらのやり方でも単位粗骨材量・単位細骨材量の値は変わりません。設計の手順として、細骨材の量をベースにするのか、粗骨材の量をベースにするのかという違いです。
最適単位粗骨材かさ容積法について、簡単に解説すると、
粗骨材の絶対容積と実積率から、かさ容積を求めて計算する方法です。
詳しくは、こちらの記事で配合計算の説明しています。
細骨材率の役割・基準(標準)
コンクリートの骨材は主に増量材としての役割を担っています。細骨材率は、増量材の比率を変えることでコンクリートのワーカビリティーをコントロールする役割を持っています。
その中でも、粘性(材料分離抵抗性)と流動性のバランスをとる役割をしています。
一般に、スランプが大きいほど細骨材率を大きくし、水セメント比が小さいほど細骨材率を小さくします。
スランプは単位水量で調整すると思われがちですが、実際には、細骨材率(s/a)を増減する事で、ある程度スランプの設定が決まってしまいます。
細骨材率(s/a)を変動させずに、単位水量だけでスランプをコントロールすると、バサバサかシャバシャバのコンクリートにしかなりません。同じスランプでもワーカビリティーの良否があるのは、細骨材率(s/a)が影響しているからです。
細骨材率に一定の基準というものはありませんが、目安となる指針があります。
細骨材率の標準値
コンクリート標準示方書(土木学会)
水セメント比55%・スランプ8cm程度のコンクリートにおける標準値
|
粗骨材の最大寸法 |
単位粗骨材かさ容積 (㎥/㎥) |
空気量 (%) |
細骨材率 (%) |
単位水量 (kg/㎥) |
| 15 | 0.58 | 7.0 | 48 | 170 |
| 20 | 0.62 | 6.0 | 45 | 165 |
| 25 | 0.67 | 5.0 | 43 | 160 |
| 40 | 0.72 | 4.0 | 40 | 155 |
JASS 5(建築学会)
普通ポルトランドセメントでAE減水剤もしくは高性能AE減水剤を使用する普通コンクリートの標準値
| 水セメント比 (%) |
スランプ (cm) |
AE減水剤 | 高性能AE減水剤 | ||
| 砕石(20mm) | 砂利(25mm) | 砕石(20mm) | 砂利(25mm) | ||
| 40〜60 | 8 12 15 18 21 |
0.66 0.65 0.64 0.60 0.56 |
0.67 0.66 0.65 0.61 0.57 |
0.67 0.66 0.65 0.61 0.57 |
0.68 0.67 0.66 0.62 0.58 |
| 65 | 8 12 15 18 21 |
0.65 0.64 0.63 0.59 0.55 |
0.66 0.65 0.64 0.60 0.56 |
||
この表を目安に配合設計を行い、コンクリートの状態で微調整をしていきます。
細骨材率に影響を及ぼす要因(単位水量、水セメント比、空気量など)
最後に、細骨材率に影響を及ぼすおもな要因をまとめて説明します。
まとめ
コンクリートの細骨材率について説明しました。


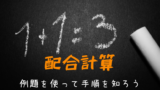




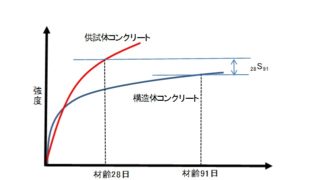
コメント