鉄筋コンクリート構造物において、鉄筋の腐食は耐荷性能や耐久性能を低下させるため、構造物の診断において、重要な指標となります。
コンクリートに含まれる塩化物イオンが、鉄筋を保護している不働態被膜を破壊し腐食を促進することはよく知られていますが、アルカリ金属の供給源としてアルカリシリカ反応の促進にも関与しています。
塩化物イオンは鉄筋の腐食とコンクリートのひび割れの両方に関与している場合もあり、塩化物イオン含有量の把握が劣化予測に対して重要となります。
塩害の意味や内容、鉄筋の腐食量について直接調査する場合については、これらの記事で説明しています。
全塩化物イオン量と可溶性塩化物イオン量の違い
塩化物イオンは「固定化・溶解」の二つの形態でコンクリート内に存在しています。
- 固定化
- セメント鉱物と反応して化合物(フリーデル氏塩)となったりセメント水和物に吸着された状態のイオン
- 溶解
- コンクリート内の細孔溶液に溶け、溶解された状態のイオン
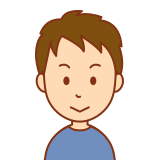
可溶性塩化物イオンはコンクリート内を自由に移動するため、鉄筋腐食に直接関与する塩化物イオンと言われています。
塩化物イオン含有量の測定方法の種類
塩化物イオン量を化学分析により測定する方法には測定原理と用いる機器や試薬によって種類があります。測定方法の代表的な手法に ついてご紹介します。
- 重量法
- 容積法
- 吸光光度法
- 電気化学的方法
- イオン成分測定方法
塩化物イオンを含む溶液の重量を測定し塩化物イオン含有量を求める方法で、主な測定方法には塩化銀滴定法があります。
試料から取り出した溶液に塩化銀溶液を加え、塩化物イオンと銀イオンを反応させ塩化銀の沈殿を生成します。この沈殿をろ過・乾燥し、重量を測定することで塩化物イオン含有量を求めることができます。
塩化物イオンを含む溶液の体積を測定し塩化物イオン含有量を求める方法で、主な測定方法にはモール法・硝酸銀第二水銀法があります。
試料から取り出した溶液に硝酸銀水溶液を滴下し、塩化物イオンと銀イオンを反応させ塩化銀の沈澱を生成します。加えた硝酸銀水溶液の体積から、試料溶液の塩化物イオン含有量を求めることができます。
終点の指示薬としてクロム酸カリウムを用います。塩化物イオンが塩化銀として沈殿しきった後に硝酸銀が滴下されると、硝酸銀とクロム酸カリウムが反応し、クロム酸銀の赤褐色の沈澱が生じます。この色の変化を終点の判定とします。
溶液中の塩化物イオンと特定の試薬との反応により、吸光度を測定することで塩化物イオン含有量を求める方法で、主な測定方法にはチオシアン酸第二水銀法、クロム酸銀法があります。
試料から取り出した溶液にチオシアン酸第二水銀を加え、塩化第二水銀とします。
あらかじめ加えた硫酸第二鉄アンモニウムと遊離したチオシアン酸イオンから生成される錯イオンの吸光度を測定し、検量線から塩化物イオン含有量を求めることができます。
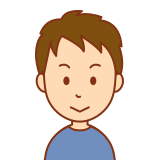
「吸光度」とは光の吸収の強さを意味し、吸光度は溶液の濃度に比例します。そのため、溶液の吸光度を測定することで、試料溶液の濃度を求めるものことができます
コンクリート試料を電気化学的な手法によって電流・電位の変化を分析し、塩化物イオン濃度を求める方法で、主な測定方法には電位差滴定法、イオン電極法、電量滴定法があります。
原理はモール法と同様で、硝酸銀水溶液を滴下する塩化物イオンの滴下沈澱法です。モール法との違いは終点の確認方法です。
指示薬による色の変化ではなく、指示電極として使用した塩化物イオン電極の電位の変化によって、終点を把握します。電気的な変化を捉えるため、微量分析にも適用できます。
イオンクロマトグラフィーを用いて塩化物イオンを分離・定量し、塩化物イオン含有量を求める方法です。
試料から取り出した溶液を分離カラム内に注入し、カラム内で各イオンに分離します。除去カラムで精製した後に、電気伝導度検出器などを用いて塩化物イオンを定量します。
塩化物イオン含有量の測定方法の手順
塩化物イオン含有量の測定では、測定するイオン量によって塩化物イオンの抽出方法に違いがあります。
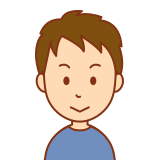
振とうとは、容器を振ったり揺れ動かし試料を混ぜたり分離させる方法です。
- 試料の採取
コア採取は塩化物イオンの流出を防ぐため乾式のコアカッターを使用し、抜き取ったコアはビニル袋などで密閉し保管します(塩化物イオンの拡散状況を知るため、部材位置や表面側などの情報をコアに記入しておく)
- 試料の調整
試料は粗骨材を含めた全量を150㎛を通る程度まで微粉砕し、上記の塩化物イオンの抽出方法によって、塩化物イオンの抽出を行う。
- 溶液の調整
抽出した溶液をろ過・洗浄をして、ろ液を水で定容し、試料溶液を作製する。
- 塩化物イオン量の測定
溶液を分取し測定を行う。

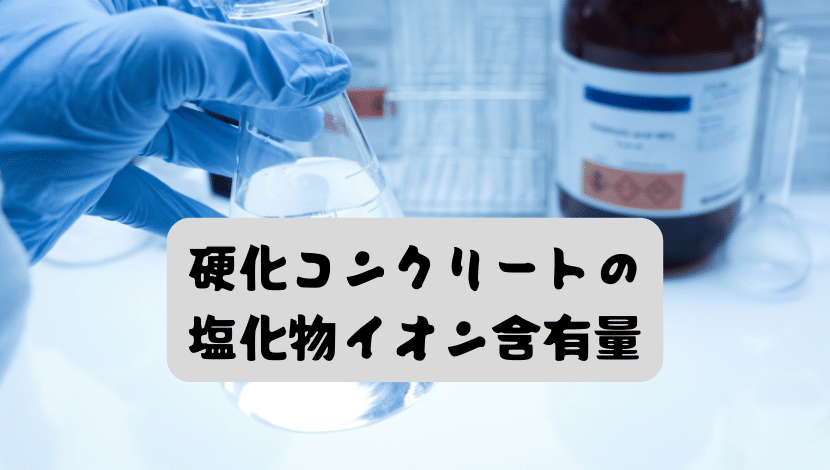
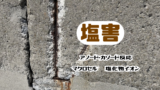
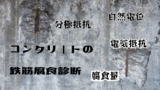




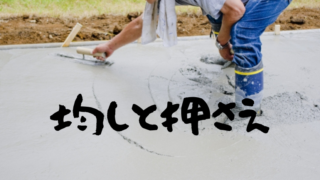
コメント