コンクリートの材料のうち、もっとも多く使用する材料です。コンクリート中の60~80%は、骨材で出来ています。コンクリートに使用する骨材は二種類あり、一般の人が砂と砂利と言っているのが、細骨材(砂)と粗骨材(砂利)です。
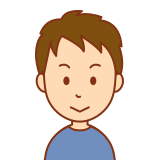
ちなみに、細骨材のみを使用したものをモルタルと呼んでいます。詳しい説明は以下の記事をご覧ください
このページでは、コンクリートの大部分を占める骨材について、説明します。
骨材の種類・分類・分け方について
冒頭で、骨材の種類は二通りに分けられると書きましたが、それはコンクリートを作る配合上での話です。骨材には、様々な種類・分類・分け方がありますから、まずはじめにそこから説明します。
細骨材と粗骨材の分け方
コンクリートを作るのに必要な材料は、セメント・水・骨材になります。骨材は粒の大きさを基準として、粒の大きなものを粗骨材(粗い)・小さなものを細骨材(細かい)として区別して使用します。
- 細骨材
- 10㎜ふるいを全量通り、5㎜ふるいを質量で85%以上通過する
- 粗骨材
- 5㎜ふるいに質量で85%以上とどまる
ひとまず、5mm以上の粒を粗骨材、5mm未満の粒を細骨材と区別していると理解してください。
製造方法による分類
次に骨材の作り方です。自然から採掘したものを天然骨材といいます。一方、自然から採掘したものを加工したり、人工的に作られたもの・産業副産物を利用したものを人工骨材と呼びます。以下がその代表的なものです。
天然骨材
川や山・海などで採取(河床や河川敷、海や海浜、丘陵地の砂れき層など)したものをいいます。採取場所によっては泥分が多いため洗浄して使用します。
粒形がよくコンクリート用骨材として良質なものが多いですが、近年は環境保護のため採取規制により使用量が減少しています。
海砂利・海砂については塩分を多く含み、未洗浄だったり洗浄が不十分であると、コンクリートの劣化原因(塩害)となるため、注意が必要です。
人工骨材
破砕や冷却・粒度調整などの工程を経て人工的に製造される骨材を言います。
砕石・砕砂とは、天然の岩石をクラッシャーという機械にかけ、コンクリート用骨材のサイズに破砕したものを言います。天然骨材に代わり、現在もっとも使用量の多い骨材になります。
スラグ骨材とは、製鉄所・発電所・焼却炉などで出る産業副産物(残りカス)を破砕・粒度調整したものを言います。
人工軽量骨材とは、頁(けつ)岩と呼ばれる膨張岩石を焼成したもの。多孔質なため、密度が軽く断熱性・吸音性に優れていますが、強度は小さい。
再生骨材
建物の解体などで生じたコンクリート塊を破砕・分級などの処理をして製造したものを言います。
再生骨材には、性能によって3つのランクに分けられます。
SDGSの観点からも、利用促進が望まれる材料ですが、再生骨材M・再生骨材Lについては、JIS A 5308では使用できず、新たにJISの認証を必要とするなど、実態として普及が進んでいるとは言えません。
重さ(密度)による分類
最後は、重さによる分け方です。コンクリートの用途や種類によっては、骨材の重さが重要となります。
普通骨材とは、密度で2.5~2.8 g/㎤程度の範囲の骨材を指し、一般的な天然骨材や人工骨材の一部が該当します。特殊な用途以外のあらゆるコンクリート向けの骨材と言えます。
軽量骨材とは、軽量コンクリートを製造する際に使われるもので、細骨材で2.3g/㎤未満、粗骨材で2.0g/㎤未満とされています。
重量骨材とは、密度で3.0 g/㎤を超えるものを指すことが多く、スラグ骨材や砕石の一部が該当します。砕石遮蔽用コンクリートや重力式擁壁など、コンクリートの重さ(自重)が有利となる場合に使用されます
骨材の岩種(石質)
近年は天然骨材が採取しずらくなっており、人工骨材である砕石・砕砂の使用が多くなっています。砕石・砕砂とは、岩石を砕いて粗骨材・細骨材の粒度に適合するように作られたものです。
その岩石にも種類があるので、代表的なものを説明します。
| 火成岩 | 安山岩 | 花崗岩 | 玄武岩 |
| 密度が大きく、強度の強いものが多い | |||
| 堆積岩 | 石灰岩 | (硬質)砂岩 | |
| 石灰岩は強度は低いが、乾燥収縮を抑える働きがある | |||
| 変成岩 | 大理石 | ||
| コンクリート用としては不向き | |||
骨材の働きについて
増量材としての働き
コンクリートとは、人工的に作られた岩石のようなものですが、セメントだけを固めてしまう事は出来ません。
セメントの水和反応によって起こる発熱・収縮を骨材が抑制することで、コンクリートがひび割れを起こさずに硬化することができます。
荷重を受ける働き
コンクリートは、セメントペーストと骨材で構成されています。そのため、コンクリートの強度は、ペーストの強度と骨材の強度の弱い方の強度になります。
そのため高強度になるほど、骨材強度が重要になります。
耐久力としての働き
コンクリートは、強度以外の強さも重要となります。温度変化や摩耗・化学的な作用・熱などに強い必要があります。
コンクリートの大部分は骨材によって形成されているため、骨材自体が耐久性・耐火性に優れていることが重要となります。
ワーカビリティ・状態をコントロールする働き
セメントペーストの状態では、水とセメントが分離し(水溶き片栗粉のような感じ)、そのままでは使えません。骨材を入れることで、分離を抑え全体を均一にする働きがあります。
また、コンクリートの流動性は、骨材の量や比率によってコントロールします。
まとめ
骨材の種類や分類、骨材の働きについて説明しました。
骨材の規格には、細かな規定がありますが、前提として骨材の種類や働きを整理しておくとより理解が深まると思います。

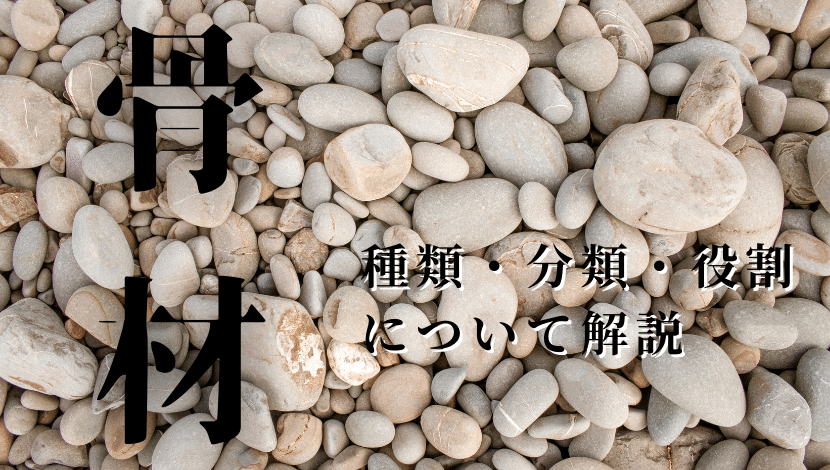





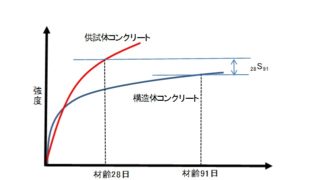
コメント